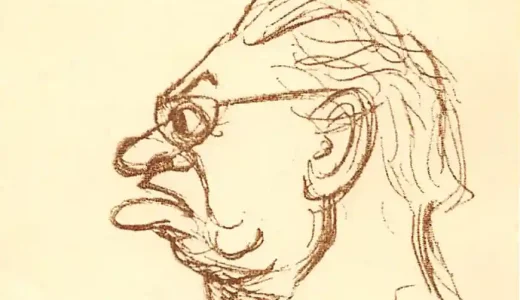京都下鴨の「潺湲亭」、谷崎潤一郎が暮らし『夢の浮橋』の舞台になった邸です。「後の潺湲亭」とも呼ばれていました。
現在名前は「石村亭」と変わりましたが、建物の趣や佇まいは当時と変わっていません。谷崎潤一郎がこよなく愛した京都「潺湲亭」を訪ねました。
後の潺湲亭
「のちのせんかんてい」と呼びます。
左京区下鴨泉川町、下鴨神社「糺の森」の東側
小道を隔てて冠木門があります。

谷崎潤一郎が1949年(昭和24年)から1956年(昭和31年)まで7年7カ月暮らした「後の潺湲亭」です。
現在は日新電機株式会社の迎賓館「石村亭」になっています。この邸を谷崎潤一郎はこよなく愛しました。
建坪はさほどでもないけれども、庭が廣くて林泉の美があり、門の前は諺蒼とした糺の森に面していた。私はこの邸を「潺湲亭」と名づけ、当時日本に滞在していた銭痩鉄氏に揮毫して貰った扁額を掲げてこの庭を限りなく愛し、毎年春と秋とには缺かさずここに戻って過す習慣になっていた。
谷崎潤一郎「高血壓症の思い出」『夢の浮橋』中公文庫、2005年、p162 より引用
この地で『潤一郎 新訳源氏物語』『少将滋幹の母』『鍵』などの名作がうまれました。
下鴨への転居
この邸へ移るまで谷崎は南禅寺に近い白川畔に住んでいました。
その家は、南禅寺の門前から永観堂や若王子の方へ行く道にあって、うしろに白川が流れてい、一番奥の八畳の間は水に沿うて建てられていて、窓の下をゆくせ々らぎの音がすわっていてもしめやかに聞えた。
谷崎潤一郎「潺湲亭」のことその他『月と狂言師』中公文庫、1981年、p152より引用
作家になる前の水上勉が1947年(昭和22年)この邸を訪ねています。
宇野先生の名刺を、下河原のお宅の玄関でお手つだいさんにさし出すと、玄関の右手の応接間へ通された。今から思うと通りに面した部屋だったのだろう。奥は白川に沿っているはずだから、川音は遠かった。
水上勉「谷崎潤一郎先生のこと」『谷崎潤一郎全集 第19巻月報』中央公論社 、1968年、p1 より引用
手狭であり白河の氾濫で石垣が損壊したため、谷崎は1949年(昭和24年)下鴨に転居しました。
「後の潺湲亭」を購入した経緯を谷崎自らが『三つの場合』で述べています。
廿四年三月廿七日、(中略) 私も持ち前の転居癖が出て今少し広い邸が欲しくなり、二條の度量衡店主塚本氏の所有である、下鴨泉川町の別壁をわれわれ夫婦と明さん夫婦と四人で見に行く。家人等は實用に不便と云ふので不賛成であったが、有名な庭師の作った林泉の趣がまことに美しく、瀧あり池あり茶席ありで、明さんがすっかり気に入り、頻りにすすめて已まないので、遂に譲り受けることに決める。
四月廿九日、天長節。南禅寺から下鴨の家に移る。爾来ここを潺湲亭と名づける。
谷崎潤一郎「明さんの場合(細雪後日譚)」『三つの場合』中央公論社、1961年、p145より引用
谷崎夫妻と娘の恵美子、夫人の妹渡辺重子、夫人の長男清治とその妻千萬子、孫のたをりの家族7名がこの邸で暮らしました。
亭号の由来
「潺湲亭」は白川畔の邸につけられた亭号です。命名には次のようないきさつがありました。
窓の外には絶えず白川の水の音がした。ふと私は、此処に住んで此の家を「潺湲居」と呼んだら、など、も思った。私はいったい「何々荘」とか「何々庵」とか大層らしい名を附ける趣味は嫌いなのであるが、でも「潺湲居」は悪くない気がした。「潺湲居」より「潺湲亭」の方がよくはないか、いや、やっぱり「潺湲居」がよいか、「居」か「亭」かと、私は暫く迷ったが、結局「亭」にした方がよさそうに思えた。私の眼には「潺湲亭」と刻した印や額の文字までが見えて来た。
谷崎潤一郎「潺湲亭」のことその他『月と狂言師』中公文庫、1981年、p153より引用
住み始める前に、中国の著名な築刻の名手である銭痩鉄氏に「潺湲亭」の額の文字を揮毫してもらったり、「わが庵は永観堂の西二丁若王子みち白川の岸」という歌を自ら詠んでいたことが記されています。京都で新生活を始める谷崎の気持ちの高ぶりが伝わります。
邸の様子
「後の潺湲亭」は『夢の浮橋』に「五位庵」として登場します。
五位庵の場所は、糺の森を西から東へ横切ったところにある。下鴨神社の社殿を左に見て、森の中の小径を少し行くと、小川にかけた幅の狭い石の橋があって、それを渡れば五位庵の門の前に出る。
谷崎潤一郎『夢の浮橋』中央文庫、2007年、P11より引用
糺の森は下鴨神社の境内にある社叢林、賀茂川と高野川の合流地点に発達した原生林で広さは12万4千平方メートル

糾の森に流れる小川にかけた幅の狭い石の橋を渡って西へ向かいます。

「石村亭」と書かれた表札の冠木門、外から建物や庭の様子は見えません。
1956年(昭和31年)日新電気株式会社が谷崎から邸を譲り受けました。「石村亭」という亭号は谷崎の命名
会社の施設として「潺湲亭」では堅すぎるため、「五位庵」と「石村亭」を提示したところ「石村亭」が採用されました。
そして、実は先達てあの邸を処分した時、後に入ってくれる人が、潺湲亭ではあまりに字が難しすぎる、何か別な名をつけてくれろと言ったので、「五位庵」と「石村亭」とを示したら「石村亭」の方を採った、それで今度の小説では「五位庵」を使うことにする、「石村亭」というのは、庭に大陸渡来らしい石の像がいくつかあったところから思いついたのだが、どちらかと言うと、池に遊びに来る五位鷺に因んでつけた「五位庵」のほうが気に入っていた、石村亭の方を選んでくれて、小説らしい方が残ってよござんした、と、ちょっとはにかんだような笑いを浮かべられた。
伊吹和子『われよりほかに ― 谷崎潤一郎最後の十二年』講談社、 1994年、p201 より引用
残った「五位庵」が後に『夢の浮橋』で使われました。
当時の邸の様子を谷崎の義理の娘渡辺千萬子が綴って います。
潺湲亭は二条の度量衡店主塚本氏が有名な庭師「植惣」に造らせた庭園で、数奇を凝らし、賛を尽くし、費用に糸目をつけず丹精を込めて造られています。六OO坪ほどの敷地を実際よりは奥深く見せて、せせらぎや添水を配した小さな池、滝、枝ぶりの良い松などが巧みに取り入れられていて、桜はもとより、つつじゃ馬酔木、山吹、藤、珍しい野木瓜の棚や葉ずれの音も優しい細い竹叢などがありました。四季折々美しい庭でした。
渡辺千萬子『落花流水―谷崎潤一郎と祖父関雪の思い出』岩波書店、2007年、p38-39より引用
「京都を訪れた際には見に行きたいので、現状のまま使ってほしい」という谷崎との約束を同社はまもり、谷崎が暮らしていたときの趣や佇まいが今も残されています。
谷崎と京都
1956年(昭和31年)12月に谷崎は熱海へ移住しました。1962年(昭和37年)亡くなる3年前に谷崎潤一郎は京都への思いを語っています。
あのまま糺の森にゐればよかったと、今でもときどきさう思ふ。さうしたら京都のあの気候にも馴れ、毎日々々京都でなければ口に出来ないおいしい物を食べて暮らして行けたのにと、よくさう思ふ。
谷崎潤一郎「京都を想う」『雪後庵夜話』中央公論社、1967年、P112より引用
離れていても京都に強い思いがあり、食べ物はできる限り京都から取りよせています。
食べる物も出来得る限り京都から運んで貰っている。肉は神戸牛や松阪牛ならぬ近江牛、これも京都から大きなかたまりで送って来る。夏でも特急で持って来て、熱海駅で落して貰う。鶏肉は今出川の鳥岩のを、腸だけ抜いて丸ごとで送らせる。魚は、鯛、ぐじ、鱧、鰆、鮎、等々を、四条のたん熊、銀閣寺の山月から、生菓子は堺町の松屋のがらん餅、深山路、鱧ずしは祇園のいづう、錦の井伝、と、大体決っている。
谷崎潤一郎「京都を想う」『雪後庵夜話』中央公論社、1967年、P112-113より引用
春と秋には京都を訪れ桜を観たり、祇園へ出かけたりして楽しんでいました。当時の京都滞在の様子を谷崎潤一郎自身が語っています。
十一日のハトで着いて、十二日の晩に、家人、義妹、千萬子、たをりの四人を伴って、先づ都をどりを見る。ここのをどりは藝よりも祇園と云ふ町の情緒と長い歴史が醸し出す氣分が身上なのである。それに前後一時間足らずで見てしまへるのも氣が利いてゐる。私たちは平安神宮や嵯峨の櫻とここ の踊りを見ないことには春が來たやうに感じない癖がついてゐるので、戦争中と病気の時とを除いて、この行事を缺かしたことがない。
谷崎潤一郎「老後の春」『 谷崎潤一郎全集 第19巻』中央公論社、 1968年、p413-414より引用
墓所も京都に定めました。東山の麓、鹿ヶ谷の法然院
墓所には鞍馬石の自然石で作られた二基の墓石が並んでいます。

向かって左の墓石には「寂」、右には「空」谷崎の自筆が彫られています。「寂」の墓石は谷崎夫妻、「空」の墓石は谷崎夫人の妹重子夫妻の墓
愛した京都に谷崎潤一郎は眠っています。